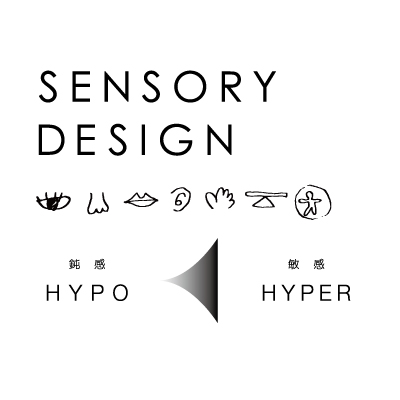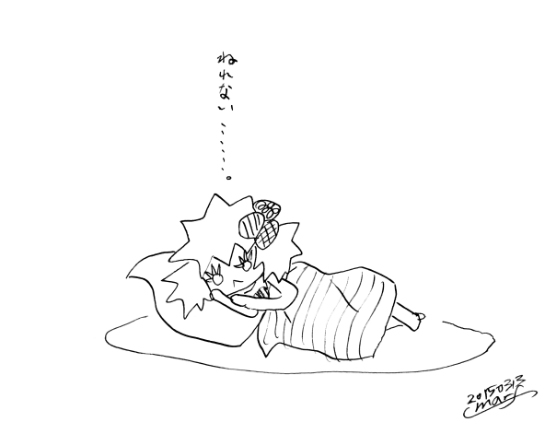プチサピエンス:センサリーアプリ『Calm』
テントント先輩のプチサピエンス 第4回
先輩タキス(画像左、以下タ):こんにちは。このコーナーでは、テントントさんの暮らしに役立つちょっとした知恵=プチサピエンスを紹介するね。
後輩るうが(画像右、以下る):よろしくおねがいします。エイプリルフールはほんと大変だったよ。緊張するしフリスク牛乳は辛いし。でも今日はひとりじゃないから楽だ。
タ:るうがちゃんあの日は本当おつかれさま。緊張はほんとやっかいだよね。テントントさんは普段からちょっとした体調不良や気になることで気を張りがちだから、相当大変だったと思うよ。勇気を出してやってくれてありがとう。
る:やるときはやるってのも、大事なことさ。
タ:エイプリルフールには間に合わなかったんだけど、お詫びに今日は緊張やパニックを和らげるセンサリーアプリを教えるよ。
る:タイミングズレズレ。さすが”あの”フリスク牛乳をおいしいと思うズレを持つ人だ…
続きを読む »